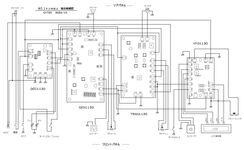「VFO1130」入荷しました。
皆さん、こんにちは。
先日から、品切れだった「VFO1130」の再販を、開始しました。
今日、秋月さんからパ-ツが届いたので、急遽パッキングしました。
よろしくお願いします。
先日から、品切れだった「VFO1130」の再販を、開始しました。
今日、秋月さんからパ-ツが届いたので、急遽パッキングしました。
よろしくお願いします。
50MHzリニアアンプ・セミキットを発売しました。
 皆さん、こんにちは。
皆さん、こんにちは。
大変お待たせしました。
発売が遅れていた、50MHzリニアアンプ「POW1130」セミキットの
販売を始めました。
Tran1130+Gen1130のセットに合わせて、設計しています。
50MHzにおいて、100mW入力で、出力は0.8W(電源12V時)に
なります。
スル-回路が入っていますので、Tran1130のアンテナ端子に調節つなぐだけで、出力アップができます。
スタンバイは、送信時の「+TX12V」を、アンプ基板のスタンバイ端子に
加えるだけです。
他のバンドでの仕様には、LPFの定数を変えてください。
入力レベルなどは、同じにしてください。
ATTが必要な場合は、基板上に実装するパタ-ンが、用意されています。
もう少しパワ-が欲しい所ですが、他のユニットに合わせて、電源が12Vなので、0.8W程度となります。
(スル-回路に使用しているリレ-が、汎用品なので損失が多少あるかもしれません。
価格は、 1set ¥6000(税込み)?送料¥350でお願いします。
なお、他のキットの送料も、郵便代が上がったため、+¥50とさせていただきます。
 皆さん、こんにちは。
皆さん、こんにちは。大変お待たせしました。
発売が遅れていた、50MHzリニアアンプ「POW1130」セミキットの
販売を始めました。
Tran1130+Gen1130のセットに合わせて、設計しています。
50MHzにおいて、100mW入力で、出力は0.8W(電源12V時)に
なります。
スル-回路が入っていますので、Tran1130のアンテナ端子に調節つなぐだけで、出力アップができます。
スタンバイは、送信時の「+TX12V」を、アンプ基板のスタンバイ端子に
加えるだけです。
他のバンドでの仕様には、LPFの定数を変えてください。
入力レベルなどは、同じにしてください。
ATTが必要な場合は、基板上に実装するパタ-ンが、用意されています。
もう少しパワ-が欲しい所ですが、他のユニットに合わせて、電源が12Vなので、0.8W程度となります。
(スル-回路に使用しているリレ-が、汎用品なので損失が多少あるかもしれません。
価格は、 1set ¥6000(税込み)?送料¥350でお願いします。
なお、他のキットの送料も、郵便代が上がったため、+¥50とさせていただきます。
100mW基準発振器
皆さん、こんにちは。
昨年、暇なときに「100mW基準発振器」という物を、製作しました。
「画像フォルダ-」へ、UPしました。
周波数は、50MHzと26MHzの物と、2setです。
26MHzは、HF帯用として、手元にあった適当なクリスタルを、使いました。
この様な物をなぜ製作したかと言うと、リニアンプ開発時、いちいち
トランシ-バ-をつなげるのが面倒で、個別に発振器を作ろうと思いました。
パワ-の校正は、オシロスコ-プを使い、ACのピ-ク電圧を測り、実効値を
求め、あとは計算により、パワ-を求めました。
そのため、精度は、家のオシロスコープ程度となります。
なかなか、高周波の電圧を測定するものがなく、オシロが一番てっとばやい
測定器となります。
(実は、デジタルオシロを使いましたが、今までのアナログオシロと違い
計算したパワ-値が、退官するパワ-値とかなりかけ離れた値を取る
など、結構難しい面もあります。デジタルオシロに関しては、詳しくない
のですが、なかなかクセがありそうな感じです)
応用としては、QRPパワ-計を作る際の信号源とか、FCZ製パワ-計の
校正とか、考えれば、まだ出てくると思います。
パワ-測定は、実はかなり難しい所があり、メ-カ-製のパワ-計も
目安程度と、考えたほうがいいと思います。
今回販売しようとしているパワ-アンプは、なんだかんだで、どうやら12V
電源で、出力は0.8Wぐらいなようです。
考えてみると、このTRでは、このぐらいが精いっぱいです。
なかなか、パワ-に対して確信が持てず(いろいろは測定をして、それぞれ
値が異なることが多かったためです。)悩みました。
結果としては、出力パワ-は、手持ちの測定器では、おおむね目安でしかな
いことが分かりました。
これでも不便はないのですが、アマチュアの悲しい性で、今出ているパワ-の
少しでも正確な値が知りたくなります。
交信が好きな人は、交信が目的なので、飛べばよくあまりパワ-に関しては
アバウトです。
自作家だけの病でしょうね。
では。
昨年、暇なときに「100mW基準発振器」という物を、製作しました。
「画像フォルダ-」へ、UPしました。
周波数は、50MHzと26MHzの物と、2setです。
26MHzは、HF帯用として、手元にあった適当なクリスタルを、使いました。
この様な物をなぜ製作したかと言うと、リニアンプ開発時、いちいち
トランシ-バ-をつなげるのが面倒で、個別に発振器を作ろうと思いました。
パワ-の校正は、オシロスコ-プを使い、ACのピ-ク電圧を測り、実効値を
求め、あとは計算により、パワ-を求めました。
そのため、精度は、家のオシロスコープ程度となります。
なかなか、高周波の電圧を測定するものがなく、オシロが一番てっとばやい
測定器となります。
(実は、デジタルオシロを使いましたが、今までのアナログオシロと違い
計算したパワ-値が、退官するパワ-値とかなりかけ離れた値を取る
など、結構難しい面もあります。デジタルオシロに関しては、詳しくない
のですが、なかなかクセがありそうな感じです)
応用としては、QRPパワ-計を作る際の信号源とか、FCZ製パワ-計の
校正とか、考えれば、まだ出てくると思います。
パワ-測定は、実はかなり難しい所があり、メ-カ-製のパワ-計も
目安程度と、考えたほうがいいと思います。
今回販売しようとしているパワ-アンプは、なんだかんだで、どうやら12V
電源で、出力は0.8Wぐらいなようです。
考えてみると、このTRでは、このぐらいが精いっぱいです。
なかなか、パワ-に対して確信が持てず(いろいろは測定をして、それぞれ
値が異なることが多かったためです。)悩みました。
結果としては、出力パワ-は、手持ちの測定器では、おおむね目安でしかな
いことが分かりました。
これでも不便はないのですが、アマチュアの悲しい性で、今出ているパワ-の
少しでも正確な値が知りたくなります。
交信が好きな人は、交信が目的なので、飛べばよくあまりパワ-に関しては
アバウトです。
自作家だけの病でしょうね。
では。
今年もよろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。
お正月から、だいぶたちますが、新年のご挨拶と言う事で。
ことしも、楽しい自作をしましょう。
1月4日に、母の葬儀があり、今はその事後処理に、追われています。
落ち着くまでには、もう少し時間がかかるようです。
50MHzのリニアンプ・キットは、部品の発注が終わり、今製作マニュアルを書き出したところです。
遅れてしまい、申し訳ないです。
さ-、2025年は、何を作りましょうか。
お正月から、だいぶたちますが、新年のご挨拶と言う事で。
ことしも、楽しい自作をしましょう。
1月4日に、母の葬儀があり、今はその事後処理に、追われています。
落ち着くまでには、もう少し時間がかかるようです。
50MHzのリニアンプ・キットは、部品の発注が終わり、今製作マニュアルを書き出したところです。
遅れてしまい、申し訳ないです。
さ-、2025年は、何を作りましょうか。
今年一年、ありがとうございました。
皆さん、こんにちは。
家の関係で、これが今年最後の、あいさつとなります。
皆さんに、HPをご覧いただき、ありがとうございました。
50MHzリニアアンプが、中途半端になってしまい、申し訳ございません。
来年いなったら、作業を迅速に進めます。
もう少し、お待ちください。
-・・・-
今年一年も、いろいろなことがありました。
年末に母が亡くなり、告別式は来年へ持ち越しとなりました。
今年の夏は、ものすごく暑かったですね。
その時期に、家をリフォ-ムしたのですが、暑さで体調を崩しました。
人の出入りで疲れたようです。今は、回復しました。
自作関係も、1130ユニットシリ-ズを中心に、ずいぶんと製作しました。
来年いなったら、未発表の実験など、いろいろと公開できると思います。
来年も、新しい工作ネタを、提供できればと思います。
よろしくお願いいたします。
PS:年始のご挨拶は、できませんので、ご了承ください。
CYTEC/JE1AHW 内田
家の関係で、これが今年最後の、あいさつとなります。
皆さんに、HPをご覧いただき、ありがとうございました。
50MHzリニアアンプが、中途半端になってしまい、申し訳ございません。
来年いなったら、作業を迅速に進めます。
もう少し、お待ちください。
-・・・-
今年一年も、いろいろなことがありました。
年末に母が亡くなり、告別式は来年へ持ち越しとなりました。
今年の夏は、ものすごく暑かったですね。
その時期に、家をリフォ-ムしたのですが、暑さで体調を崩しました。
人の出入りで疲れたようです。今は、回復しました。
自作関係も、1130ユニットシリ-ズを中心に、ずいぶんと製作しました。
来年いなったら、未発表の実験など、いろいろと公開できると思います。
来年も、新しい工作ネタを、提供できればと思います。
よろしくお願いいたします。
PS:年始のご挨拶は、できませんので、ご了承ください。
CYTEC/JE1AHW 内田
リニアンプ・キットが遅れます。
皆さん、こんにちは。
MilkyWay6用の、1Wリニアアンプ・キットの発売が、少し遅れます。
理由は、母が入院しまして、いろいろと時間がとられるからです。
申し訳ないですが、ちょっと時間を頂きたいと思います。
MilkyWay6用の、1Wリニアアンプ・キットの発売が、少し遅れます。
理由は、母が入院しまして、いろいろと時間がとられるからです。
申し訳ないですが、ちょっと時間を頂きたいと思います。
2SC1970の件
皆さん、こんにちは。
先日、リニアアンプに使う、2SC1970の入手ができないと書きましたが、
その後、 小林さん/横浜、冨川さん/那須塩原 お二人のご尽力で
入手できました。
MilkeyWay6の、アンプ「POW1130」のキットを、作ります。
ただし、TRの数が限られているので、いつものように少量生産となります。
これで、100mW->1W が実現します。
もう少しお待ちください。
先日、リニアアンプに使う、2SC1970の入手ができないと書きましたが、
その後、 小林さん/横浜、冨川さん/那須塩原 お二人のご尽力で
入手できました。
MilkeyWay6の、アンプ「POW1130」のキットを、作ります。
ただし、TRの数が限られているので、いつものように少量生産となります。
これで、100mW->1W が実現します。
もう少しお待ちください。
久々の書き込みです。
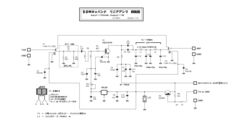 皆さん、こんにちは。
皆さん、こんにちは。
しばらくぶりの、書き込みになります。
今年の夏は、本当に暑かったようで、結構ダメ-ジを受けました。
胃の調子が悪く、食欲もなくなり、やる気も起きず、自作も、しばらく
お休みでした。
先週あたりから、食欲も出てきて、なんとなく復帰できそうです。
こんなに長い、夏バテ状態は、初めてです。
50MHzトランシ-バ-「Milkyway6」の、出力が100mWなので、
もう少しパワ-アップしたいと考えていました。
手持ちのTRの中で、2SC1970を使って、1W出力が出ました。
しかし、この石が入手できず、現在どうするか、悩んでいます。
HFですと、適当な石でも、1Wは出ますが、50MHzとなると、175MHzが増幅できる石でないと、まともに出力が出てきません。
どうしますかね~~。
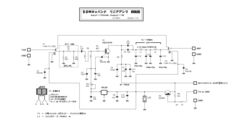 皆さん、こんにちは。
皆さん、こんにちは。しばらくぶりの、書き込みになります。
今年の夏は、本当に暑かったようで、結構ダメ-ジを受けました。
胃の調子が悪く、食欲もなくなり、やる気も起きず、自作も、しばらく
お休みでした。
先週あたりから、食欲も出てきて、なんとなく復帰できそうです。
こんなに長い、夏バテ状態は、初めてです。
50MHzトランシ-バ-「Milkyway6」の、出力が100mWなので、
もう少しパワ-アップしたいと考えていました。
手持ちのTRの中で、2SC1970を使って、1W出力が出ました。
しかし、この石が入手できず、現在どうするか、悩んでいます。
HFですと、適当な石でも、1Wは出ますが、50MHzとなると、175MHzが増幅できる石でないと、まともに出力が出てきません。
どうしますかね~~。
Milkyway6 各基板総合結線図
2SK241を発見しました。
先ほど、書きましたが、行方不明の2SK241を、発見しました。
もう少しは、1130シリ-ズが続けられます。
よくある話ですが、いつもと違うパーツボックスに、しまっていました。
お騒がせしました。
もう少しは、1130シリ-ズが続けられます。
よくある話ですが、いつもと違うパーツボックスに、しまっていました。
お騒がせしました。

 2025/01/16(Thu) 15:13
2025/01/16(Thu) 15:13