ケース
こんばんは、
以前重宝していた上下嵌合式のアルミケース、メーカーは忘れましたが、
サトー電気から飛んでみたらどこにもありませんでした
ALIEXPRESSにあるのはアルミではなく鉄製なんですわ、試しにひとつ
発注してみました
穴あけはステンレス用のドリルやホールソーならなんとかなると
思うんですけど・・・
以前重宝していた上下嵌合式のアルミケース、メーカーは忘れましたが、
サトー電気から飛んでみたらどこにもありませんでした
ALIEXPRESSにあるのはアルミではなく鉄製なんですわ、試しにひとつ
発注してみました
穴あけはステンレス用のドリルやホールソーならなんとかなると
思うんですけど・・・
Re: ケース
 JL1KRA
JL1KRA  2026/01/09(Fri) 11:15 No.45
2026/01/09(Fri) 11:15 No.45
テイシンのケースも微妙にラインナップが減っている感じです。
鉄製の中華ケース、加工が苦しいです。角穴も厳しい、、、
よく使うのは多めに買うしかないですね
鉄製の中華ケース、加工が苦しいです。角穴も厳しい、、、
よく使うのは多めに買うしかないですね
 JL1KRA
JL1KRA  2026/01/09(Fri) 11:15 No.45
2026/01/09(Fri) 11:15 No.45
Re: ケース
こんばんは、
お初におめもじ致します
まんずアルミケースはいいのほど入手が難しくなりました
最後はJG3ADQさんに倣って板金加工ですかねえ・・・
お初におめもじ致します
まんずアルミケースはいいのほど入手が難しくなりました
最後はJG3ADQさんに倣って板金加工ですかねえ・・・
アルミケ-スが無くなる???
皆さん、こんにちは。
最近知ったのですが、アルミケ-スを製造していたところが、
生産をやめるようです。
それは、「リード」です。
それと、タカチなども、取り扱い品もぬを減らしているような感じ
がします。私が好きな、YM-250が売っていないのです。
摂津金属さんは、まだ大丈夫なようですが、安心はできません。
個人が使う、アルミケ-ス市場は、もともとそれほど大きくはないと思います。
近年、自作をする方も減り、ますます事業として成り立たなくなってきたのでしょう。
金属部材の値上げもあるのでしょうね。
なんかだんだん、寂しい話しか聞かなくなりましたね。
最近知ったのですが、アルミケ-スを製造していたところが、
生産をやめるようです。
それは、「リード」です。
それと、タカチなども、取り扱い品もぬを減らしているような感じ
がします。私が好きな、YM-250が売っていないのです。
摂津金属さんは、まだ大丈夫なようですが、安心はできません。
個人が使う、アルミケ-ス市場は、もともとそれほど大きくはないと思います。
近年、自作をする方も減り、ますます事業として成り立たなくなってきたのでしょう。
金属部材の値上げもあるのでしょうね。
なんかだんだん、寂しい話しか聞かなくなりましたね。
Re: アルミケ-スが無くなる???
 釣巻
釣巻  2026/01/07(Wed) 14:29 No.41
2026/01/07(Wed) 14:29 No.41
リードは生産終了です。その在庫を千石通商が買い取り、時々点灯で販売しています。
 釣巻
釣巻  2026/01/07(Wed) 14:29 No.41
2026/01/07(Wed) 14:29 No.41
Re: アルミケ-スが無くなる???
 釣巻
釣巻  2026/01/07(Wed) 14:33 No.42
2026/01/07(Wed) 14:33 No.42
点灯→店頭
 釣巻
釣巻  2026/01/07(Wed) 14:33 No.42
2026/01/07(Wed) 14:33 No.42
Re: アルミケ-スが無くなる???
釣巻さん、おめでとうございます。
今年も、よろしくお願いいたします。
そうですか。千石さんが、在庫を購入したのですか。
リ-ドの、ちょっと高さのある四角いケ-スは、よく使いました。
いずれにしても、無くなるのは困りますね。
今年も、よろしくお願いいたします。
そうですか。千石さんが、在庫を購入したのですか。
リ-ドの、ちょっと高さのある四角いケ-スは、よく使いました。
いずれにしても、無くなるのは困りますね。
謹賀新年
皆さん、あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
毎年、正月にはあれをやろうこれをやろうと思うのですが、
結局、何もできないで終わってしまいます。
今年も同じです・・・・。
バンドを覗くと、今日は結構にぎやかで、往年のアマチュア無線を
思い出し、うれしくなります。
今年もよろしくお願いいたします。
毎年、正月にはあれをやろうこれをやろうと思うのですが、
結局、何もできないで終わってしまいます。
今年も同じです・・・・。
バンドを覗くと、今日は結構にぎやかで、往年のアマチュア無線を
思い出し、うれしくなります。
Re: 謹賀新年
 JL1KRA
JL1KRA  2026/01/04(Sun) 22:16 No.38
2026/01/04(Sun) 22:16 No.38
時々の書き込みになりますが、本年もよろしくお願いいたします。
Luna6-RXとペアになるTXが出てきたらいいですね。数100mWあると実用的です。
最近は手持ちのキットで手いっぱいになっていますが、
またCYTECさんのキットを作りたいと思っています。
お正月は掃除のあとで休むのでいいのだと思います。
どちらかというと5月のGWは一番ゆっくり作業が進みます。
Luna6-RXとペアになるTXが出てきたらいいですね。数100mWあると実用的です。
最近は手持ちのキットで手いっぱいになっていますが、
またCYTECさんのキットを作りたいと思っています。
お正月は掃除のあとで休むのでいいのだと思います。
どちらかというと5月のGWは一番ゆっくり作業が進みます。
 JL1KRA
JL1KRA  2026/01/04(Sun) 22:16 No.38
2026/01/04(Sun) 22:16 No.38
Re: 謹賀新年
中島さん、あけましておめでとうございます。
お久しぶりですね。お元気でしたか?
以前お会いしてからもう何年も経ち、お互い年を重ねましたね。
今年は50MHzのAMトランシーバー製作を目標にしようと思います。
幸い、隣県の自作家の方と知り合いになり、QSOも可能な距離なので、その方との共通の目標になっています。
とにかくAMモードでは相手がなかなかいないため、今回はQSO相手が見つかってから始まるプロジェクトです。
Luna6を作ったときに、約80mW出力の送信機も製作しました。
ただ、低電力変調のため変調波がきれいではなく、もう少し研究が必要だと感じています。
さて、どうなることやら。
お久しぶりですね。お元気でしたか?
以前お会いしてからもう何年も経ち、お互い年を重ねましたね。
今年は50MHzのAMトランシーバー製作を目標にしようと思います。
幸い、隣県の自作家の方と知り合いになり、QSOも可能な距離なので、その方との共通の目標になっています。
とにかくAMモードでは相手がなかなかいないため、今回はQSO相手が見つかってから始まるプロジェクトです。
Luna6を作ったときに、約80mW出力の送信機も製作しました。
ただ、低電力変調のため変調波がきれいではなく、もう少し研究が必要だと感じています。
さて、どうなることやら。
今年1年、ありがとうございました。
皆さん、いよいよ今年も、終わりですね。
今年一年、CYTECのHPを、ご覧いただき、ありがとうございました。
今年一年は、ほとんどを50MHzトランシ-バ-「Milkeyway6」で、過ぎました。
そんな中、自分で制作したトランシ-バ-・キット同士での、QSOが出来、大変思い出深い都市となりました。
CYTECをもう20年以上やってきましたが、反j馬手の危険です。
来年は、50MHzAMでQSOしてみたいと話しており、たぶんAMに挑戦となると思います。
AMでのQSOは、開局時代からなく、思い出深いものがあり、ぜひ
やってみたと思います。
(受信部は、もうすでに公開してキット化しています。)
毎年、いつまでやれるかと思っていますが、いろいろな人とお知り合いになり、いろいろと力を与えてもらい、何とかまだ続けていられます。感謝いたします。
では、来年もよろしくお願いいたします。
よいお年をお迎えください。
2025/12 CYTEC 内田
今年一年、CYTECのHPを、ご覧いただき、ありがとうございました。
今年一年は、ほとんどを50MHzトランシ-バ-「Milkeyway6」で、過ぎました。
そんな中、自分で制作したトランシ-バ-・キット同士での、QSOが出来、大変思い出深い都市となりました。
CYTECをもう20年以上やってきましたが、反j馬手の危険です。
来年は、50MHzAMでQSOしてみたいと話しており、たぶんAMに挑戦となると思います。
AMでのQSOは、開局時代からなく、思い出深いものがあり、ぜひ
やってみたと思います。
(受信部は、もうすでに公開してキット化しています。)
毎年、いつまでやれるかと思っていますが、いろいろな人とお知り合いになり、いろいろと力を与えてもらい、何とかまだ続けていられます。感謝いたします。
では、来年もよろしくお願いいたします。
よいお年をお迎えください。
2025/12 CYTEC 内田
回路図違っていました。
下記かろ図で、トランスの電圧が16Vになっていますが、
使用したトランスは12Vでした。
つい希望を書いてしましました。
使用したトランスは12Vでした。
つい希望を書いてしましました。
Re: 回路図違っていました。
 釣巻
釣巻  2025/12/15(Mon) 23:22 No.30
2025/12/15(Mon) 23:22 No.30
ご無沙汰しています。
早速ですが、LM317のデータシートを見ると0.5Aで約1.8V、1Aで約2Vの入出力電圧差が必要になっています。13.8V出力の場合、0.5Aで15.6V,1Aで15.8Vの入力電圧が最低必要です。
トランスが12Vだとブリッジの電圧降下も結構あるので入力電圧は15Vを下回っているのではないでしょうか。
釈迦に説法かと思いますが。
早速ですが、LM317のデータシートを見ると0.5Aで約1.8V、1Aで約2Vの入出力電圧差が必要になっています。13.8V出力の場合、0.5Aで15.6V,1Aで15.8Vの入力電圧が最低必要です。
トランスが12Vだとブリッジの電圧降下も結構あるので入力電圧は15Vを下回っているのではないでしょうか。
釈迦に説法かと思いますが。
 釣巻
釣巻  2025/12/15(Mon) 23:22 No.30
2025/12/15(Mon) 23:22 No.30
Re: 回路図違っていました。
 釣巻さん、こんにちは。
釣巻さん、こんにちは。
お久しぶりですね。お元気ですか?。
LM317に関しての情報をありがとうございます。
ちゃんと、デ-タシ-トを見れば、書いてあるんですね。
デ-タシ-トは、ほとんどピンアサインの確認が多いです。
普通の3端子でも、2Vの電圧性必要ですね。
やはり、トランスには、16Vぐらいのがいいみたいです。
そこで、LM317を本来の使い方にして、可変電源に改良しました。
出力電圧=12.5Vで、リニアンプにつなぎ規定出力を出した時
4%の電圧降下でした。
つまり、出力電圧は、0.5V降下で12Vでした。
やはり釣巻さんの言われるように、入力電圧不足が原因だったのですね。
この電圧測定で気が付いたのですが、デジタルテスタ-は、分解能がいいですね。
アナログテスタ-(昔からある物)で測定尾すると、ほとんど電圧降下が分かりません。
ほんの少し指針が動く程度です。
テスタ-のほうが適当で良い場合もありますね。
釣巻さん、よろしくです。
 釣巻さん、こんにちは。
釣巻さん、こんにちは。お久しぶりですね。お元気ですか?。
LM317に関しての情報をありがとうございます。
ちゃんと、デ-タシ-トを見れば、書いてあるんですね。
デ-タシ-トは、ほとんどピンアサインの確認が多いです。
普通の3端子でも、2Vの電圧性必要ですね。
やはり、トランスには、16Vぐらいのがいいみたいです。
そこで、LM317を本来の使い方にして、可変電源に改良しました。
出力電圧=12.5Vで、リニアンプにつなぎ規定出力を出した時
4%の電圧降下でした。
つまり、出力電圧は、0.5V降下で12Vでした。
やはり釣巻さんの言われるように、入力電圧不足が原因だったのですね。
この電圧測定で気が付いたのですが、デジタルテスタ-は、分解能がいいですね。
アナログテスタ-(昔からある物)で測定尾すると、ほとんど電圧降下が分かりません。
ほんの少し指針が動く程度です。
テスタ-のほうが適当で良い場合もありますね。
釣巻さん、よろしくです。
Re: 回路図違っていました。
 釣巻
釣巻  2025/12/17(Wed) 19:22 No.33
2025/12/17(Wed) 19:22 No.33
相変わらず時々鏝を暖めて楽しんでいます。フラックスの匂いを嗅がないと禁断症状?がでますので。
LM317のデータシートでは、1.5A出力時のレギュレーションは標準で0.1%、最悪で0.5%です。入力電圧が14V程度になっていませんか?ざっと計算するとAC12Vを整流した場合、12Vx1.3-0.7V*2で14.2v程度になるかと思います。
LM317のデータシートでは、1.5A出力時のレギュレーションは標準で0.1%、最悪で0.5%です。入力電圧が14V程度になっていませんか?ざっと計算するとAC12Vを整流した場合、12Vx1.3-0.7V*2で14.2v程度になるかと思います。
 釣巻
釣巻  2025/12/17(Wed) 19:22 No.33
2025/12/17(Wed) 19:22 No.33
Re: 回路図違っていました。
釣巻さん、こんにちは。
>>相変わらず時々鏝を暖めて楽しんでいます。フラックスの匂いを嗅がないと禁断症
>>状?がでますので。
釣巻さん、半田こてを温めるのは、貴重な作業ですね。
最近は、サイトを見ても目新しい自作品や、情報も少なくなってきています。
この分ですと、自作派が滅びてしまうのではと思いうときがります。
フラックスのにおいも、最近尾ハンダと昔とでは、違いますね。
昔は松脂系の様でした。(合成でしょうが、茶色をしていました。)
最近のは、あまり良い匂いではないですね。
LM317は、かなり性能が良いようですね。
現状トランスの規格が、12Vしか手元にないので、これ以上の改善は難しいですね。
トランスがあれば交換しても良いのですが、たぶん今のケ-スに入らなくなると思います。
いつもは、秋月さんで購入した12V/5Aクラスのスイッチング電源を、愛用しています。5W出力ですと、結構使えます。
やはり、小さくて軽くて、スイッチング電源はいいですね。
>>相変わらず時々鏝を暖めて楽しんでいます。フラックスの匂いを嗅がないと禁断症
>>状?がでますので。
釣巻さん、半田こてを温めるのは、貴重な作業ですね。
最近は、サイトを見ても目新しい自作品や、情報も少なくなってきています。
この分ですと、自作派が滅びてしまうのではと思いうときがります。
フラックスのにおいも、最近尾ハンダと昔とでは、違いますね。
昔は松脂系の様でした。(合成でしょうが、茶色をしていました。)
最近のは、あまり良い匂いではないですね。
LM317は、かなり性能が良いようですね。
現状トランスの規格が、12Vしか手元にないので、これ以上の改善は難しいですね。
トランスがあれば交換しても良いのですが、たぶん今のケ-スに入らなくなると思います。
いつもは、秋月さんで購入した12V/5Aクラスのスイッチング電源を、愛用しています。5W出力ですと、結構使えます。
やはり、小さくて軽くて、スイッチング電源はいいですね。
電源装置の写真をUPしました。
リニアアンプ用に製作した、電源を「画像フォルダ-」へUPしました。
すべてジャンク品の集まりで、ケ-スも穴をふさいで塗装して使っています。
そのため、ぐちゃぐちゃです。
あまり出来が良くないのですが、忘備録としてUPしました。
すべてジャンク品の集まりで、ケ-スも穴をふさいで塗装して使っています。
そのため、ぐちゃぐちゃです。
あまり出来が良くないのですが、忘備録としてUPしました。
ヒマなときの電源製作
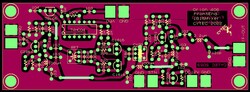 みなさん、こんにちは。
みなさん、こんにちは。
製作の大きな課題がなくなり、ちょっと手が空いたので、ジャンク箱の中を見て
トランスが有ったので、電源を製作してみました。
電源は今までに、何台製作したことでしょう。
ただ、10A以下のもので、大型電源はトランスの関係で、自作したことは
有りません。
ちょこちょこと知った、小さな電源ばかりです。
今回は、LM317Tと言う可変型の定電圧ICが有ったので、13.8V固定の
電源にしてみました。
回路図の様に、1K,10Kでほぼ13.8Vになります。
今まで、12Vを中心として自作してきましたが、世間ではどうも、13.8Vが
標準なようです。
また、先日製作した、「Venus64」用に、専用として使えるようにしました。
結果的には、12vでも、13.8vでも出力は大きくは変わりませんでした。
ちょっとは上がるかと期待していましたが、がっかり。
例えば、15vぐらいを供給すれば、出力UPができるかもしれません。
ドレインの負荷が一定なので、電圧を変えてもあまり変わらないのかと思います。
最近は、電源など製作しないので、ACコ-ドに良い物がなく、再使用です。
ブリッジダイオ-ドも、探し回って、古い電源から外した再生品です。
今時分、電源など製作している人はいないのでしょうね。
やはり、スイッチング電源が、軽く、小さく、パワ-があっていいですね。
電流は、トランスに書いてあった、1Aが上限のはずです。
しかし、リニアをつなぎ、キャリアを出すと、電圧が下がります。少しですが。
何が原因か。
リニアの電流は、1A以下なはずです。
思い当たるのは、トランスのAC出力が、12Vなのを、整流して13.8Vにしている事
が原因かもそれません。16Vぐらいの出力を持つトランスを、使うべきでしょうね。
なかなか、良い規格のトランスは、ないです。
たかが電源、されど電源でした。
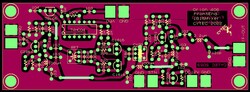 みなさん、こんにちは。
みなさん、こんにちは。製作の大きな課題がなくなり、ちょっと手が空いたので、ジャンク箱の中を見て
トランスが有ったので、電源を製作してみました。
電源は今までに、何台製作したことでしょう。
ただ、10A以下のもので、大型電源はトランスの関係で、自作したことは
有りません。
ちょこちょこと知った、小さな電源ばかりです。
今回は、LM317Tと言う可変型の定電圧ICが有ったので、13.8V固定の
電源にしてみました。
回路図の様に、1K,10Kでほぼ13.8Vになります。
今まで、12Vを中心として自作してきましたが、世間ではどうも、13.8Vが
標準なようです。
また、先日製作した、「Venus64」用に、専用として使えるようにしました。
結果的には、12vでも、13.8vでも出力は大きくは変わりませんでした。
ちょっとは上がるかと期待していましたが、がっかり。
例えば、15vぐらいを供給すれば、出力UPができるかもしれません。
ドレインの負荷が一定なので、電圧を変えてもあまり変わらないのかと思います。
最近は、電源など製作しないので、ACコ-ドに良い物がなく、再使用です。
ブリッジダイオ-ドも、探し回って、古い電源から外した再生品です。
今時分、電源など製作している人はいないのでしょうね。
やはり、スイッチング電源が、軽く、小さく、パワ-があっていいですね。
電流は、トランスに書いてあった、1Aが上限のはずです。
しかし、リニアをつなぎ、キャリアを出すと、電圧が下がります。少しですが。
何が原因か。
リニアの電流は、1A以下なはずです。
思い当たるのは、トランスのAC出力が、12Vなのを、整流して13.8Vにしている事
が原因かもそれません。16Vぐらいの出力を持つトランスを、使うべきでしょうね。
なかなか、良い規格のトランスは、ないです。
たかが電源、されど電源でした。
FET6mリニアンプ「Venus64」デ-タをUP
みなさん、こんにちは。
Milkeyway 6のパワ-アップを図り製作した、FETリニアンプ「Venus64」の
デ-タを、CYTECの表紙部と画像フォルダ-に、UPしました。
出力4Wとそれほどパワ-アップにはなっていませんが、多少は効果が
有ると思います。
50MHzは、やはり高さのある、ゲインがあるアンテナが、一番ですね。
(HFもそうですが、50MHzはより感じます)
Milkeyway 6のパワ-アップを図り製作した、FETリニアンプ「Venus64」の
デ-タを、CYTECの表紙部と画像フォルダ-に、UPしました。
出力4Wとそれほどパワ-アップにはなっていませんが、多少は効果が
有ると思います。
50MHzは、やはり高さのある、ゲインがあるアンテナが、一番ですね。
(HFもそうですが、50MHzはより感じます)
PO-dbm025 表示しない 原因と訂正です。
みなさん、こんにちは。
先日、PO-dBm025が、表示しないと言う事がありました。
原因が、分かりました。
使用しているLCD(AQM-1602)のコントラスト調整は、ソフト内で設定します。
デジタル的な設定なので、設定値が必ずれただけでも、表示しなくなります。
私が、使用したLCDのコントラストを調整しましたが、その値が須古井大きすぎたようで、表示の範囲から外れていたようです。
現在、コントラストの設定を変更して、CYTECの表紙部からDLするファイルを、
入れ替えました。
たぶんこの設定で、誰でもトラブルなく使えると思います。
以前、ダウンロ-ドした方は、再度ダウンロードしてください。
先日、PO-dBm025が、表示しないと言う事がありました。
原因が、分かりました。
使用しているLCD(AQM-1602)のコントラスト調整は、ソフト内で設定します。
デジタル的な設定なので、設定値が必ずれただけでも、表示しなくなります。
私が、使用したLCDのコントラストを調整しましたが、その値が須古井大きすぎたようで、表示の範囲から外れていたようです。
現在、コントラストの設定を変更して、CYTECの表紙部からDLするファイルを、
入れ替えました。
たぶんこの設定で、誰でもトラブルなく使えると思います。
以前、ダウンロ-ドした方は、再度ダウンロードしてください。
MilkeyWay6とQSOしました。
みなさん、こんにちは。
日曜日に、50MHzでMilkeyway6を製作された方と、QSOしました。
この方は、茨城県在中の方で、拙宅へも何度も来られている方です。
MilkeyWay6のキットを作られて、完成したとのことで、QSOしてみました。
私が使ったリグは、残念ながらその時は、MilkeyWay6ではなく、
自作のCosm6000でした。
2Way自作機同士のQSOはできました。
今度は、MilkeyWay6同士の2Way-QSOを計画しています。
今まで、自作機同士のQSOは、結構ありましたが、
自分で開発した無線機とのQSOは初めてで、感激でした。
日曜日に、50MHzでMilkeyway6を製作された方と、QSOしました。
この方は、茨城県在中の方で、拙宅へも何度も来られている方です。
MilkeyWay6のキットを作られて、完成したとのことで、QSOしてみました。
私が使ったリグは、残念ながらその時は、MilkeyWay6ではなく、
自作のCosm6000でした。
2Way自作機同士のQSOはできました。
今度は、MilkeyWay6同士の2Way-QSOを計画しています。
今まで、自作機同士のQSOは、結構ありましたが、
自分で開発した無線機とのQSOは初めてで、感激でした。
